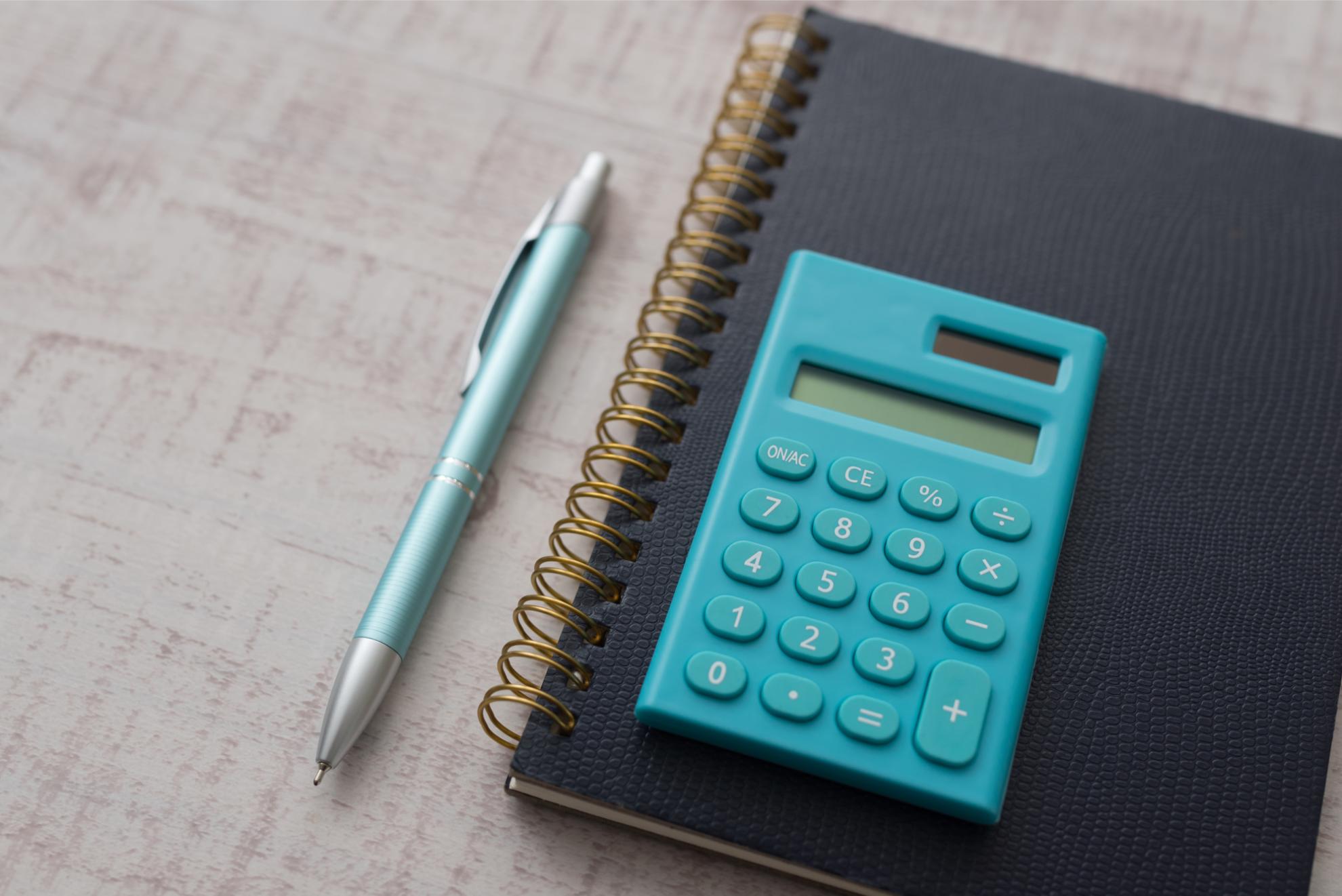土地活用における納税猶予制度とは?メリット・デメリットや適用時のポイント

土地活用で適用できる納税猶予制度について、詳しく知りたい方も多いのではないでしょうか。土地の特徴や種類によって使える制度は異なるため、事前に把握しておくことが大切です。
今回は、土地活用における納税猶予制度を詳しく解説したうえで、制度適用時のメリット・デメリット、ポイントなども紹介します。納税猶予制度を適用して、良好なキャッシュフローを維持しながら土地活用を行いたいという方は、ぜひご覧ください。
目次
土地活用における納税猶予制度とは

土地活用における納税猶予とは、相続税などの納付を一定期間延長できる制度のことです。例えば、農地を相続した場合、一定の要件を満たすことで相続税の納付期間に猶予が与えられます。
ここでは、生産緑地と農地等の納税猶予制度の概要や、その他の土地に関する納税猶予制度について解説します。
なお、土地の相続税や売却のタイミングなどについて知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
2,000万円の土地の相続税はいくら?相続の流れや控除・特例も紹介
相続した土地を3年以内に売却すべき? 適用できる税金の特例制度などを解説
生産緑地の納税猶予制度
生産緑地とは、良好な都市環境の形成を目的とした、市街化区域内の農地を指します。市街化区域は、おおむね10年以内の市街化などが見込まれる区域のことです。
生産緑地を相続して農業を行う場合は、終身営農(生涯農業を続けること)を条件に相続税が免除される納税猶予制度を適用できるケースがあります。
終身営農以外にも、一定要件を満たして生産緑地を貸借する場合は、納税猶予が継続されます。
農地等の納税猶予制度
農地等の納税猶予制度は、被相続人が営農または特定貸付け等を行っていた農地等を、一定の相続人が取得して引き続き農業を営んだり、特定貸付け等を行ったりする場合に適用される制度です。
農業投資価格(農地等が恒久的に農業で使われる場合の価格)を超える部分の相続税額について、営農または特定貸付け等を継続している限り、納税が猶予されます。
その他の土地に関する納税猶予制度
その他の土地に関する納税猶予制度として、山林、事業用地が対象のものについても確認しておきましょう。
山林に関する制度では、特定森林経営計画が定められている区域内の山林を、相続や遺贈により取得した相続人が経営を行う場合、相続税額の80%の納税が猶予されます。
また、事業用地の制度では、被相続人の特定事業用資産(宅地・建物など)を、相続や遺贈により取得した場合、一定要件下において、この資産にかかわる贈与税・相続税の納税が猶予されます。「個人版事業承継税制」とも呼ばれる制度で、2019年1月1日から2028年12月31日の間に贈与・相続された特定事業用資産が対象です。
【土地活用】納税猶予制度のメリット・デメリット

土地活用における納税猶予制度には、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。それぞれ紹介します。
メリット
納税猶予制度を適用することで、以下のメリットがあります。
- 納税負担を一時的に減らせる
- 相続税などが免除されるケースがある
納税猶予制度では、相続税などの納税負担を一時的に減らせるため、土地活用におけるキャッシュフローの安定性を保ちやすくなります。相続した土地によっては、数十万円から数千万円の相続税が課されるケースもあるため、納税に対する猶予が設けられるのは大きな魅力といえます。
また、相続税などが免除されるケースがあることもメリットです。例えば、農地等の納税猶予に関する特例適用を受けている場合、一定要件下で農業を20年継続したり、農業相続人が亡くなったりした時に納税が免除されます。
デメリット
納税猶予制度には、以下のようなデメリットもあります。
- 営農・営業等の義務が課される
- 特例要件を満たさなくなると納税義務が発生する
前述のとおり、納税猶予を継続するために、相続などによって取得した土地での営農・営業等の義務が課されます。ただし、一定要件下において貸付けを行う場合でも、制度適用が継続されるケースがあるため、それぞれの制度の詳細を確認しておくことが大切です。
また、特例要件を満たさなくなると納税義務が発生することもデメリットといえます。例えば、個人版事業承継税制によって納税が猶予されている場合、事業の廃止などに至った際、贈与税・相続税の全部または一部と、利子税を納付する必要があります。
土地活用における納税猶予制度のポイント
ここからは、土地活用において、納税猶予制度を利用する際のポイントを紹介します。
申請前に必要書類を準備しておく
納税猶予に関する制度を利用するには、必要書類の準備が不可欠です。例として、農地等の納税猶予の適用を受けるにあたり、相続税の申告時に必要な主な書類を以下に示します。
- 被相続人・相続人に関する戸籍の謄本
- 遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続税の納税猶予に関する適格者証明書
- その他特例の適用要件を確認する書類
- 担保提供書及び担保提供関係書類(※担保提供関係書類の主なもの)
・登記事項証明書(登記簿謄本)
・固定資産評価証明書など特例農地等の評価の明細
・抵当権設定に必要な書類を提出する旨の申出書
参考:国税庁「(参考)相続税の申告の際に提出していただく主な書類」
上記で挙げた書類のほか、特例農地等のうちに都市営農農地等がある場合は、そのことを証する市長(区長)の証明書なども必要です。
納税猶予期間を延長できるケースがある
制度によっては、納税猶予の期間を延長できるケースがあります。例えば、生産緑地の場合、都市計画の告示日から30年が経過すると、納税猶予が適用されなくなります。しかし、特定生産緑地の指定を受ける場合は、税制特例措置を10年ごとに更新可能です。
なお、特定生産緑地の指定を受けない場合も、現世代に限り相続税の納税猶予は継続され、次の相続における納税猶予が適用されない仕組みとなっています。
自身に合った土地活用法を検討する
納税猶予の適用を受ける土地を継承した際は、自身の投資手法に見合った土地活用を検討することが重要です。
例えば、特定事業用資産として土地を相続した場合、現状の投資手法のほかに、別の土地活用が適している可能性もあります。アパート経営や駐車場経営など、土地活用の種類は豊富です。
自身が取得した土地に最適な活用法を選び、安定した収益を得るためにも、信頼の置ける不動産会社への相談がおすすめです。
土地活用のアイデアや成功のポイントについては、以下の記事をご参照ください。
空いている土地で収入アップ!土地活用アイデア6選と成功させるポイント
まとめ
納税猶予制度には、生産緑地や事業用地など土地の種類に応じた制度がありますが、いずれにしても適用条件を入念に確認しておくことが大切です。また、土地によっては、現行の活用法以外を適用したほうがより大きな収益につながる可能性もあります。
「土地をスムーズに子どもへ相続させる方法を知りたい」「相続した土地の活用法がわからない」などのお悩みを抱えている方は、ぜひ一誠商事にご相談ください。認定相続コンサルタントが多数在籍している当社では、士業とも連携しつつ、オーナーのお悩み解決に向けてワンストップでサポートいたします。
また、地域密着の不動産会社として蓄積したノウハウを活かし、不動産売却や賃貸経営などに関するサポートにも対応可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
お持ちの土地を活用しませんか?
有効活用は大きく「貸す」「売る」「買う」の3つに分けられます。
ご自身に合った土地活用の方法を提案させていただきます。
ぜひお気軽にご相談ください。

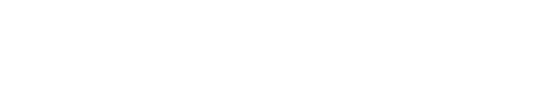
記事の監修者:一誠商事編集部
一誠商事株式会社が運営する情報サイト編集部。
不動産売買・賃貸経営・土地活用・不動産相続から快適な暮らしや住まいのことまで、不動産に関する幅広いお役立ち情報を発信しています。
創業50年、茨城県南・県央エリアで
地域密着型の不動産会社
一誠商事は、創業50年を迎えた地域密着型の不動産会社です。賃貸・管理・売買・保険・リフォームを取り扱っており、お客様のお悩み事をワンストップで解決いたします。
所有しているアパート・マンションの空室が多くて困っている、空き家の管理を依頼したい、自宅を売却したい、住み替えを検討している等、不動産に関することならなんでもご相談ください。